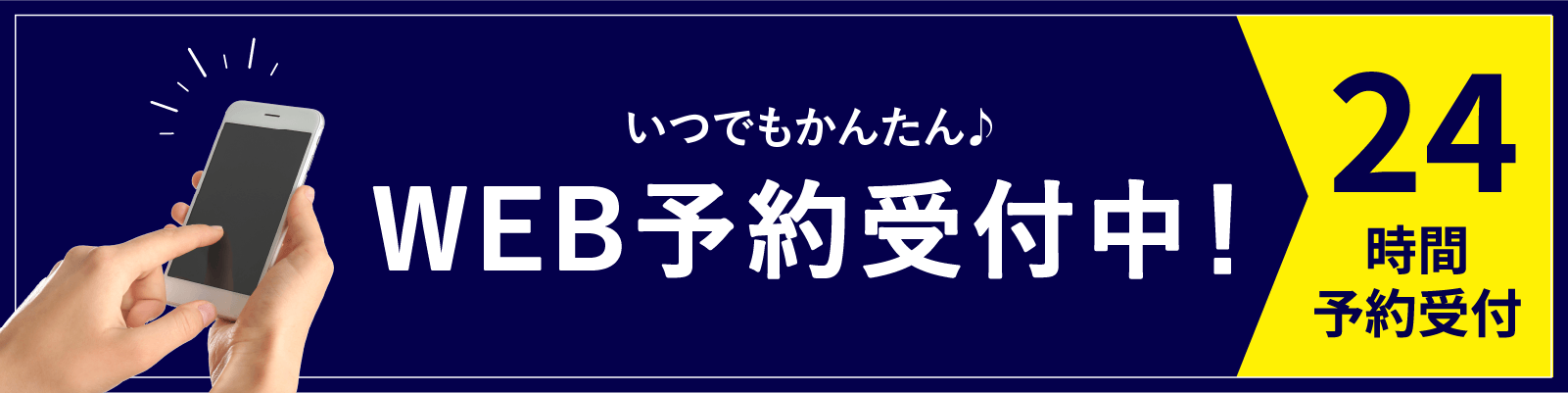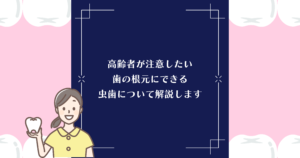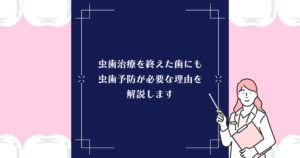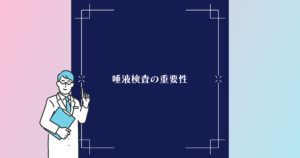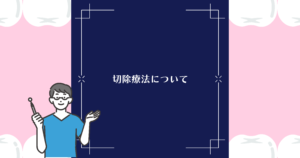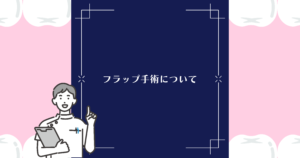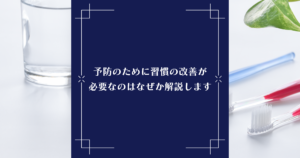
近年、虫歯になってから治療を受けるのではなく、虫歯にならないよう予防する予防歯科を重視する人が増えています。
虫歯予防のために予防歯科に通うことは大切ですが、それだけではなく、日常の習慣から改善していくことも大切です。
予防歯科の第一歩として、どのように習慣を改善すればいいのか解説します。
食事の改善点
虫歯になる原因の1つが食事であるため、食事についても見直しが必要です。
例えば、食後、ある程度時間が経ってから歯磨きをしている場合には、食後すぐに歯磨きをするよう改善しましょう。
食べたものが口の中に残っていると、虫歯の原因菌が栄養にして酸を出し、歯を溶かします。
食後すぐに歯磨きをすれば、口内にかけらを残さずきれいにできるため、虫歯の原因菌に栄養を与えることは無くなります。
また、飲食のタイミングも見直してみましょう。
例えば、ダラダラ食べをしている場合には注意が必要です。
虫歯菌は少量の糖分でも活動するため、テレビや動画などを観ながらダラダラと長い時間をかけて食事をしたり、仕事中に甘い飲み物や食べ物を口にし続けたりすると、口内が酸性に傾いてしまいます。
口内を中性の状態に戻すには、何も口にしない状態を一定時間続けなければなりません。
長時間食事を続けると、口内が酸性の状態に傾いたままになり、歯が溶ける恐れがあります。
防ぐためにも、食事やおやつの時間をしっかりと決め、それ以外の時間には糖分が含まれる飲食物を口にしないようメリハリをつけましょう。
歯にダメージを与えない
改善の必要がある習慣として、歯のくいしばりや歯ぎしりが挙げられます。
食いしばりや歯ぎしりが続くと、痛みが生じたり歯が擦り減ったりするからです。
重いものを持ち上げる時など力を入れる場面では、歯を食いしばります。
また、睡眠中に歯ぎしりをしている人もいるでしょう。
食いしばりは意識して改善できるものの、歯ぎしりは防げないため、改善よりもダメージを防ぐ方法を考えましょう。
歯ぎしりを防ぐには、歯科医院で作成できる専用マウスピースの利用がおすすめです。
就寝時に装着すると、歯ぎしりによるダメージを防ぐことができます。
呼吸方法に注意する
改善したい習慣の一つが、口呼吸です。
唾液は口内を中性に保つ働きがあり、酸性の環境を好む虫歯の原因菌の働きを阻害します。
しかし、口呼吸をすると口内が乾燥して唾液の分泌量が減少するため、虫歯の原因菌の働きが活発になります。
虫歯予防のためにも、普段から鼻呼吸を意識しましょう。
まとめ
虫歯や歯周病を予防する予防歯科の効果を高めるためには、生活習慣の改善も必要です。
改善するべき生活習慣として、食生活と歯ぎしり、食いしばり、呼吸方法などが挙げられます。
1つずつ、改善するべき点を確認して、普段から意識しましょう。
難しい場合は、歯科医院で相談してみてください。
成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。
患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております。
【ネット予約可・公式】成城学園前の歯医者|Kデンタルクリニック成城
日付: 2024年2月13日 カテゴリ:予防歯科