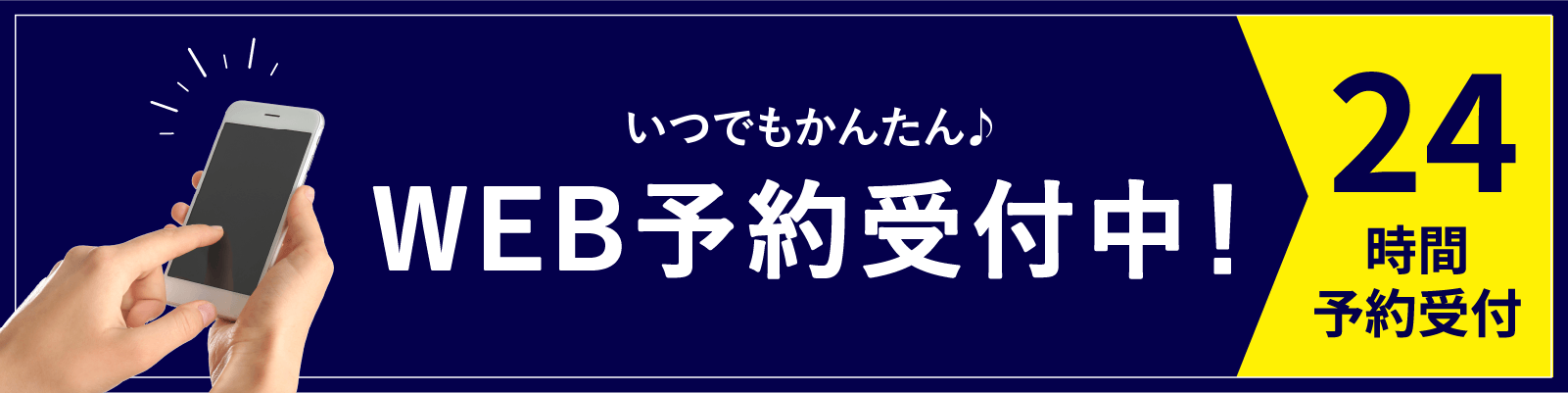高齢者になると口腔機能が弱まる「オーラルフレイル」によってうまく飲み込めず誤嚥になることが多くなります。
それに伴い、誤嚥性肺炎のリスクも高くなってしまうでしょう。
誤嚥を防ぐための代表的な訓練の1つに「パタカラ」というものがあるのをご存じでしょうか?
パタカラとは何か、解説します。
パタカラとは?
パタカラとは、「パ」「タ」「カ」「ラ」の4文字を連続で発音する口の体操で、口周りの筋肉や舌の機能を鍛えることを目的としています。
それだけでなく、嚥下機能の向上や誤嚥予防、唾液分泌の促進、発音の改善などにも効果があるのです。
医療や介護の現場で広く取り入れられており、子供から高齢者まで実践可能で、全身の健康維持にもつながるのがメリットです。
パタカラ体操は、口を大きく開けて「パ」「タ」「カ」「ラ」の文字を大きな声で、一音ずつはっきりと発音します。
「パ」は唇の筋肉を鍛えて食べこぼしを防ぐ効果があり、「タ」には舌の筋肉を鍛えて食べ物を押しつぶす力を向上させる効果があります。
「カ」は喉の奥の筋肉を鍛えて誤嚥やむせを防ぎ、飲み込みをスムーズにする働きがあり、「ラ」は舌の筋肉を鍛え、食べ物を口の中でまとめる能力を高めるのです。
食事の際に使う筋肉を鍛えるため、パタカラ体操を行うのは食前の1日3回程度が理想です。
また、「Patakara」(パタカラ)という医療器具から考えられた顔の表情筋を鍛えるマウスピースもあります。
元々はリハビリを必要とする方向けに歯科医院で開発されたものですが、現在は市販もされており、体操とともに使用されることもあるようです。
美容目的でも使用されており、Patakaraで表情筋を鍛えることで唾液が出やすくなり、食べ物を飲み込みやすくなるという効果が期待できるのです。
また、口が開けやすくなり咀嚼もしやすくなります。
ただし、正しく使用しないと効果はありません。
使用方法としては、唇と歯の間に器具を装着します。
歯茎にあたって痛みがある場合には、器具前方についているロープを引っ張りながら口を閉じるといいでしょう。
口を「うー」と突き出しながらしっかりとくわえ、下あごに梅干しのようなしわができるまで唇に力を入れるのがポイントです。
1回3分、1日4回の使用が目安となります。
パタカラの副次効果
パタカラ体操を行うことで、嚥下機能以外にもさまざまな効果があります。
例えば鼻呼吸や脳血流の増加を促す効果もあるのです。
顔の筋肉を鍛えることで引き締まった顔や小顔効果も期待でき、舌の筋力低下を防ぐことで、舌根沈下によるいびきの改善にもつながります。
ただし、効果を実感するには継続して行わなければなりません。
入浴時などに毎日の習慣として取り入れると続けやすいででしょう。
パタカラ体操は、口腔ケアの一環として多くの医療・介護施設で実施されている信頼性の高い体操です。
ぜひ一度試してみてください。
まとめ
パタカラ体操は、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発生することで口腔機能を高め、嚥下などをスムーズに行えるようにして誤嚥を防ぐことができます。
医療や介護の現場でも導入されている信頼性の高い体操で、食前やお風呂に入っている間など、毎日習慣づけて続けていくことで効果を発揮します。
表情筋トレーニングのための「Patakara」というマウスピースもあり、併用することでより効果が発揮されるでしょう。
成城で予防歯科をお考えの際には、『Kデンタルクリニック成城』にご相談下さい。
患者様と向き合い、可能な限り歯を傷つけない治療法をご提案させて頂きます。
スタッフ一同、お待ちしております。